【第12回】第2章 人体の働きと医薬品 目、鼻、耳等の感覚器官 1)目
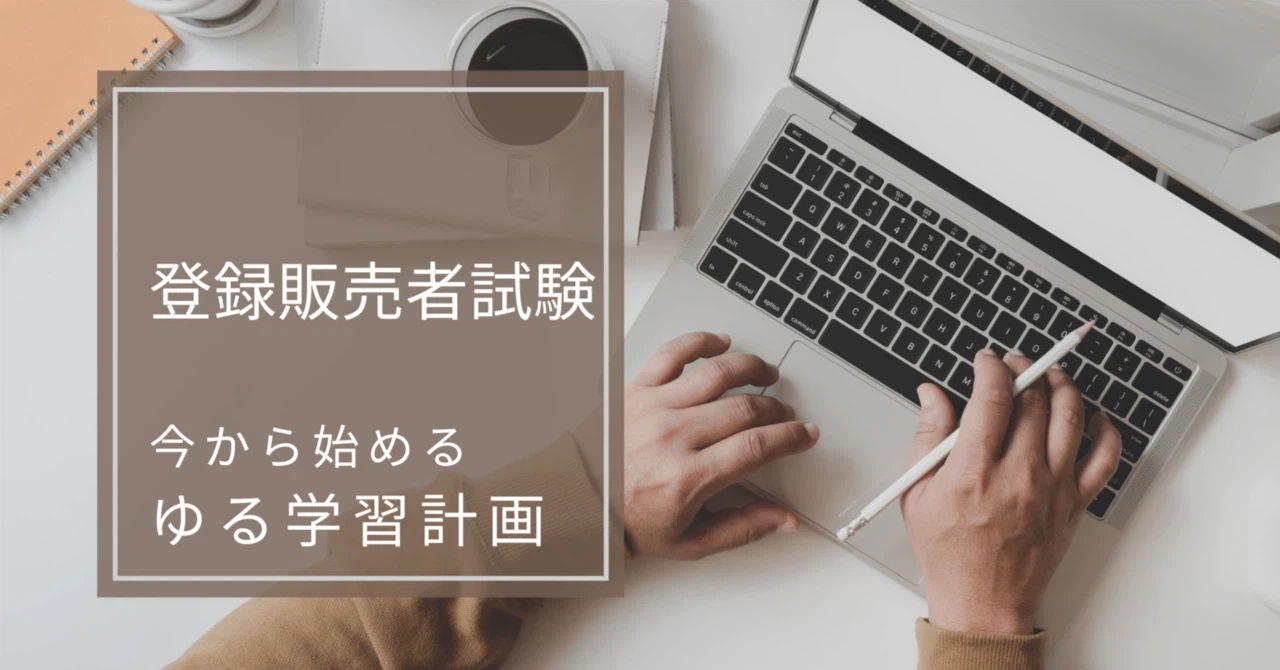
目、鼻、耳等の感覚器官
みなさんこんにちは。
登録販売者のためのゆる学習講座第12回。
今日は「見る」ということについて。見えるということはいったいどうやって見えるのか、一緒に目の中を旅してみましょう。目はただモノを見るだけじゃなくて、光を集めたり、ぼやけを直したり、暗い場所でも見やすくしたり、本当に働き者なんです。
(アフィリエイトリンクを利用しています)
1.目の組織と働き
- 角膜(かくまく)
目の一番前、透明な膜です。光を最初に受けとめ、曲げる(=屈折する)ことで光を中に導く入口の役割。 - 強膜(きょうまく)
角膜以外の目の外側を覆う白い部分。「白目」の主なところ。目の形を保つ支え、安全な盾みたいな存在。 - 房水(ぼうすい)
角膜と水晶体の間(前房)にある透明な液体。栄養を運んだり、目の中の圧(眼圧)を調整します。 - 虹彩(こうさい)
瞳の色に見える部分。瞳孔を大きくしたり小さくしたりして光の量を調節。 - 瞳孔(どうこう)
明るいところでは小さく、暗いところでは大きくなって光を取り込む通り道。 - 水晶体(すいしょうたい)
遠くや近くを見るときにピントを合わせるレンズのようなもの。 - 毛様体(もうようたい)
水晶体を支える輪っかの筋肉+組織。チン小帯を通して水晶体を引っ張ったり緩めたりし、ピントを調節。房水も作ります。 - 硝子体(しょうしたい)
水晶体の後ろ側、網膜まで満たす透明なゼリー状のもの。光が通る通り道をきれいに保ち、目の内部の形を支えるクッション。 - 網膜(もうまく)
目の奥の壁。視細胞が並び、光を電気信号に変えます。 - 視細胞
- 桿体細胞(かんたいさいぼう):明暗を感じる細胞。暗いところでぼんやりでも“何かがある”を感じられます。
- 錐体細胞(すいたいさいぼう):色の識別を担当。明るいところで色や細かい形をはっきり見ます。
- 夜盲症(やもうしょう)
暗いところで見えにくくなる状態。杆体細胞の働きやビタミンA不足が原因になりやすいです。
2.ものが見える仕組み
想像してみてください。朝、窓から差し込む光を感じて目を開けるところからスタートです。光(可視光線)が角膜を通り、房水を経て虹彩と瞳孔へ。瞳孔は明るさに応じて大きさを変え、光の量を調整します。
光は水晶体というレンズに入り、遠くを見ると薄く、近くを見ると厚くなり、ピントを合わせます。その後、硝子体を通って網膜に届きます。網膜の視細胞が光を信号に変え、視神経を通して脳へ。桿体細胞は明暗を、錐体細胞は色を伝え、脳で「見る」感覚が完成します。
豆知識
- ビタミンA不足で桿体細胞の働きが落ちると夜盲症になることがあります。暗い場所での運転等には注意。
- 年を取ると水晶体の弾力が低下してピント調節がにぶくなる「老眼」が起きます。毛様体‐水晶体系の調節力が弱くなるためです。
- 紫外線に長時間さらされると、角膜や網膜にダメージが。雪に反射する光で角膜が焼けるように感じる「雪眼炎」もあります。
3. 眼瞼・結膜・涙器・眼筋(目を守り、動かすサポート)
眼瞼(がんけん)
「まぶた」は医学的には眼瞼(がんけん)と呼びます。普段あたりまえのように瞬きをしていますが、これはとても大事な働きなんです。瞬きのたびに涙が目全体に広がり、乾燥を防いだり異物を洗い流したりしてくれます。
- 光やほこり、乾燥から目を守るカバーの役割
- 瞬きで涙を広げ、目の表面を潤す
- 睡眠中には目を閉じて、休息と保護をしてくれる
涙器(るいき)
「涙器(るいき)」は、涙をつくる涙腺(るいせん)と、涙を排出する涙道(るいどう)から成り立ちます。涙は血液の液体成分である血漿(けっしょう)からつくられ、涙腺で分泌されます。そしてまぶたの縁にある涙点(小さな穴)から涙道を通り、最終的には鼻へと流れていきます。だから、泣いたときに鼻水も一緒に出るんですね。
涙液の働きはとても多彩です:
- ゴミやほこり、刺激性の化学物質を洗い流す
- 角膜に酸素や栄養分を供給する
- 角膜や結膜で生じた老廃物を洗い流す
- 角膜表面を滑らかに保ち、鮮明な視覚を助ける
- リゾチーム・免疫グロブリンなどを含み、感染から守る
涙は単なる「水」ではなく、目の健康を守る万能なバリアなんです。
眼筋(がんきん)
私たちが自由に視線を動かせるのは、眼筋(がんきん)のおかげです。目の周りには6本の筋肉(外眼筋)があり、上下・左右・斜めと自在に眼球を動かしています。両目の眼筋が協力して、物を立体的に見ることも可能になります。
眼精疲労(がんせいひろう)
パソコンやスマホを長時間見ていると「目がしょぼしょぼする」「頭痛がする」なんてこと、ありませんか?これは眼精疲労(がんせいひろう)と呼ばれる状態です。
- ピント調節を行う毛様体筋や、眼球を動かす眼筋が酷使される
- 涙の分泌が減って目が乾燥し、さらに疲れやすくなる
- 姿勢やストレスも影響して、肩こり・頭痛につながることも
対策としては、適度に目を休ませる「20-20-20ルール(20分ごとに20フィート先を20秒見る)」や、意識的に瞬きをして涙を広げることが役立ちます。
まとめ(目を守る・支える仕組み)
- 眼瞼(まぶた)が光やほこりから守り、涙を広げる
- 涙器が涙をつくり・流し、潤いや感染防御を担う
- 眼筋が視線を自由に動かす
- これらの働きがバランスを崩すと眼精疲労につながる
つまり「守る・潤す・動かす」がセットになって、私たちの目は健康に働いているんです。
ここまでで、目のまわりを守ったり、動かしたりする仕組みを一緒に見てきましたね。
「まぶたが涙でうるおして、眼筋が動きを支えて…なるほど、目ってチームワークで働いているんだ!」という感じがつかめたでしょうか。
それでは、実際に試験に出た問題で確認してみましょう。
過去問にチャレンジ!(令和7年度・関西広域連合 後半)
【問67】
目に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
- a 目を使う作業を続けると、眼筋の疲労のほか、遠近の焦点調節を行っている硝子体の疲労などが起こる。
- b 雪眼炎は、眼球が紫外線を含む光に長時間曝されることにより、網膜の上皮が損傷を起こした状態である。
- c 視細胞が光を感じる反応にはビタミンAが不可欠であるため、不足すると夜間視力の低下が生じる。
- d 睡眠中は涙液分泌が多いため、滞留した老廃物に粘液や脂分が混じって眼脂(目やに)となる。
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
| 2 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |
| 3 | 正 | 誤 | 正 | 正 |
| 4 | 誤 | 誤 | 正 | 誤 |
| 5 | 正 | 正 | 誤 | 正 |
目に優しいこと始めてみませんか?
(アフィリエイトリンクを利用しています)





