【第14回】第2章 人体の働きと医薬品 目、鼻、耳等の感覚器官 3)耳
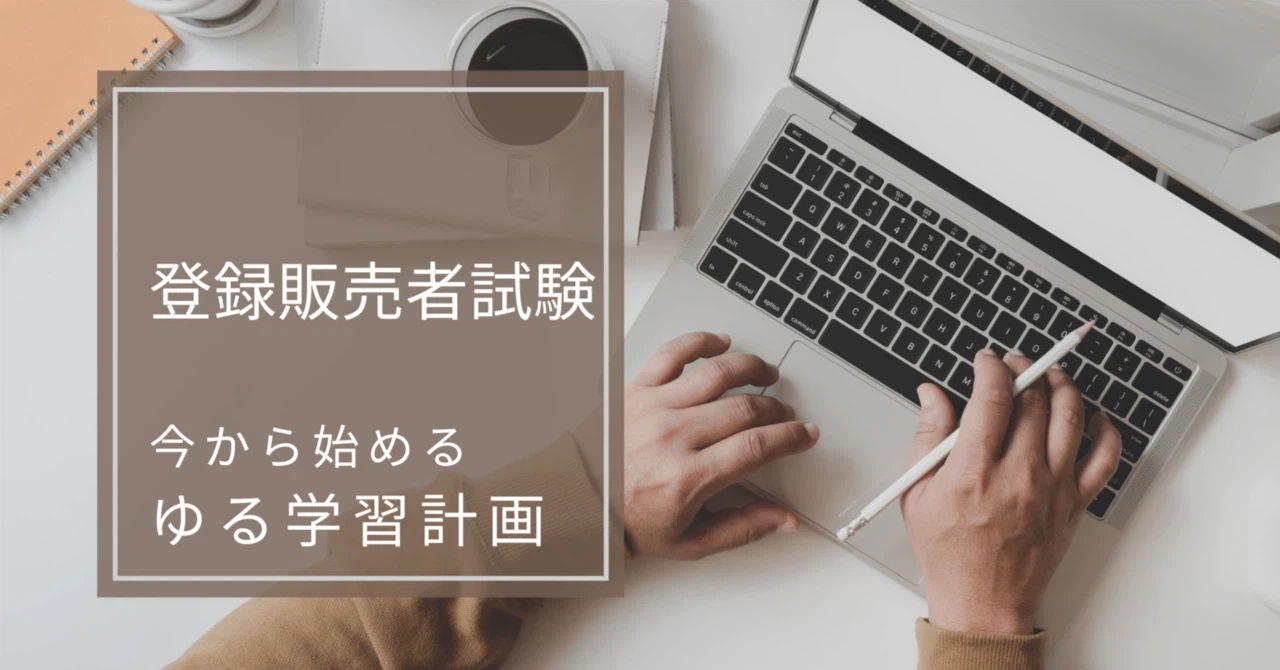
こんにちは。登録販売者のためのゆる学習講座第14回。
前回は「鼻」の構造と働きについて見てきました。
鼻は外界から空気中のにおい分子をとらえる役割があり、嗅覚として大切な感覚器ですね。
今回は、その感覚器の仲間である「耳」について、音を感じる仕組みと、バランス感覚を司る部分まで、しっかり理解していきましょう。
大丈夫、順を追って見ていけば、耳の構造もグッと身近に感じられますよ。ではさっそく見ていきましょう!
耳の働きと構造(聴覚と平衡感覚
私たちの体にある感覚器官のひとつ「耳」。
耳は 音を聞く(聴覚) だけでなく、体のバランスを保つ(平衡感覚) という、とても大切な働きもしています。
しかも左右に1つずつあることで、音の方向や距離感までキャッチできるんです。
私たちが音楽を楽しんだり、誰かの声の方向をすぐに振り向けるのは、耳のおかげなんですね。
耳は大きく分けて 外耳(がいじ)・中耳(ちゅうじ)・内耳(ないじ) の3つの部分からできています。
では、それぞれの役割をやさしく見ていきましょう。
外耳(がいじ)
外耳は、顔の横に見えている部分から鼓膜までを指します。
外から入ってきた音を集めて、鼓膜に届けるのが役割です。
- 耳介(じかい)
頭の横に出ている部分(いわゆる耳たぶ)。やわらかい軟骨でできていて、音を集める「パラボラアンテナ」のような働きをしています。 - 外耳道(がいじどう)
耳介で集めた音を鼓膜まで届ける“音の通り道”。途中には 耳垢腺(じこうせん) があり、分泌される耳垢が耳の中を守ってくれます。 - 鼓膜(こまく)
外耳と中耳の境にある薄い膜で、音の振動をキャッチする“太鼓の皮”のような存在です。
中耳(ちゅうじ)
中耳は、鼓膜の奥にある小さな空間で、音の振動を内耳へ伝える中継地点です。
- 耳小骨(じしょうこつ)
ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨の3つの小さな骨でできています。鼓膜の振動を大きくして内耳に伝える「拡声器」のような役割をしています。 - 耳管(じかん)
鼻の奥とつながっていて、中耳の気圧を調整する働きがあります。飛行機に乗ったときに耳が“つーん”とするのは、この耳管が関係しているんですよ。

小さなこどもは耳管が太く短くて水平に近いため、鼻腔からウイルスや細菌が侵入し感染がおこりやすい。中耳炎などになりやすいのもそのためなんですね。
内耳(ないじ)
内耳は、耳の「情報センター」と呼べる場所。音を感じる 聴覚器官 と、体のバランスを感じる 平衡器官 が集まっています。
- 蝸牛(かぎゅう/聴覚器官)
貝殻のように渦を巻いた形をしていて、中はリンパ液で満たされています。耳小骨から伝わった振動がリンパ液を震わせ、その振動が感覚毛を持つ聴細胞を刺激します。そこから神経を通じて脳に伝わり、私たちは「音」として認識するのです。 - 前庭(ぜんてい)と半規管(平衡器官)
・耳石器官(じせききかん):水平や上下(垂直方向)の動きを感知
・半規管:体の回転や傾きを感知
→ どちらもリンパ液の動きを利用して、体のバランスを保っています。
👉 実は「乗り物酔い(動揺病)」は、この平衡感覚が繰り返し刺激されて混乱することで起きる現象なんです。
まとめ
耳は「音を聞く」だけでなく、「体のバランスを感じる」という二つの大切な働きを持っています。
外耳・中耳・内耳、それぞれがしっかり役割を分担して、私たちの生活をサポートしているんですね。
それではさっそく耳に関する過去問を解いてみましょう!
過去問にチャレンジ!(令和5年度・愛知県)
【問8】
耳に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
- a 外耳は、側頭部から突出した耳介と、耳介で集められた音を鼓膜まで伝導する外耳道からなる。
- b 中耳は、聴覚器官である蝸牛と、平衡器官である前庭の2つの部分からなる。
- c 小さな子供では、耳管が太く短くて、走行が水平に近いため、鼻腔からウイルスや細菌が侵入し感染が起こりやすい。
- d 平衡器官である前庭の内部はリンパ液で満たされており、水平・垂直方向の加速度を感知する半規管と、体の回転や傾きを感知する耳石器官に分けられる。
| a | b | c | d | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 誤 | 正 | 正 | 誤 |
| 2 | 正 | 正 | 誤 | 正 |
| 3 | 正 | 誤 | 正 | 誤 |
| 4 | 誤 | 正 | 誤 | 正 |
| 5 | 正 | 誤 | 正 | 正 |



