【第6回】第2章 人体の働きと医薬品 呼吸器系
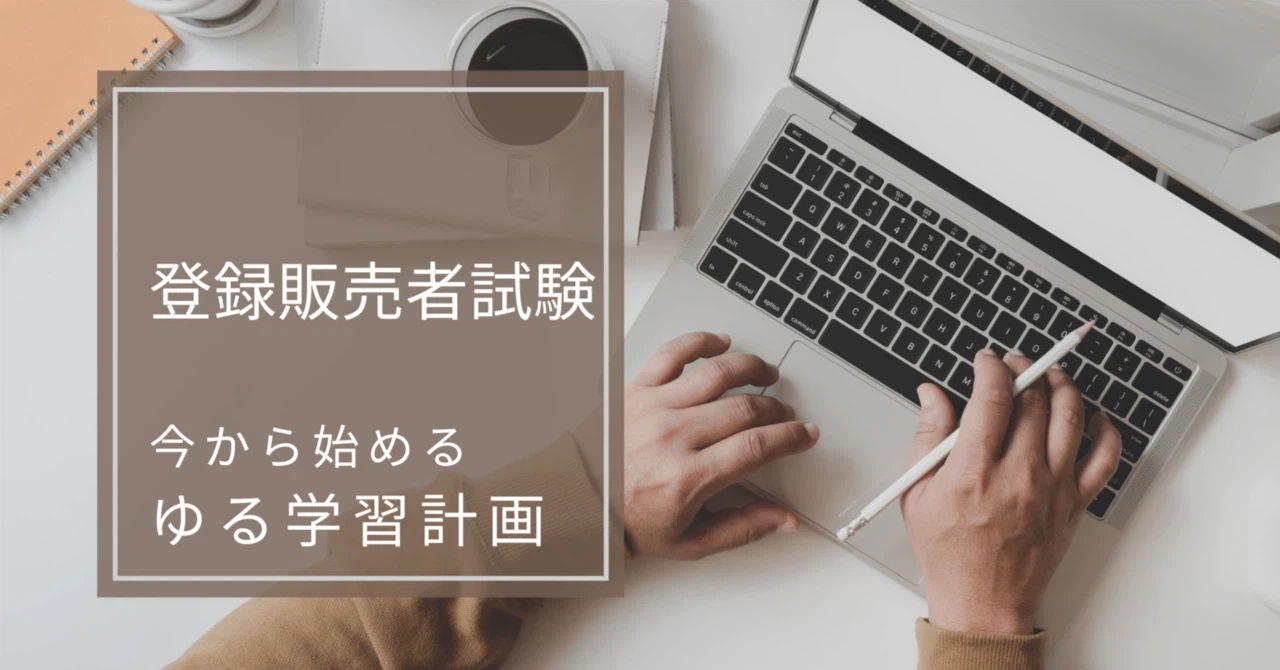
呼吸器系|空気の通り道と肺のしくみをやさしく解説
1. 呼吸器系って何をするところ?
呼吸器系は、簡単にいうと「空気(酸素)を体に取り込み、いらなくなった二酸化炭素を外に出す」ためのしくみです。
空気の通り道は「上気道」と「下気道」に分けて覚えるとスッキリします!
- 上気道:鼻腔~咽頭~喉頭まで
- 下気道:気管~気管支~肺まで
では順番に見ていきましょう!
(a) 鼻腔(びくう)
鼻の奥にある空気の通り道で、呼吸の入り口となる場所です。
主な働き:
- 吸い込んだ空気を温めたり、加湿したり、ホコリを取り除いたりする「空気清浄機」のような役割をしています。
- 粘膜には「リゾチーム」という抗菌物質が含まれており、細菌などの侵入を防ぎます(←ここ、よく出ます!)。
📝 ポイント:
鼻毛や粘膜がバリアの役目をしていて、風邪やウイルスから体を守る第一防衛ラインでもあります。
(b) 咽頭(いんとう)
鼻と口の奥にある部分で、食べ物と空気が通る共通の道。
口を開けたときに見える「のど」の奥の方ですね。
主な働き:
- 呼吸時は空気を喉頭(こうとう)へ送る。
- 飲食時は食道へ導く。
この分ける働きのおかげで、空気と食べ物が正しく運ばれます。
📝 ポイント:
咽頭の役割を担う部分では、誤って食べ物が気管に入らないよう「フタのような構造(喉頭蓋)」も登場しますよ。
🛡️ 咽頭にある「扁桃(へんとう)」って何?
咽頭の周囲には、「扁桃(へんとう)」と呼ばれる免疫の関所のような組織があります。
中でも有名なのが、「口を開けると見える白っぽいかたまり」=口蓋扁桃(こうがいへんとう)です
扁桃の役割:
- 体に入ってくる細菌やウイルスをキャッチして処理する防衛ライン。
- 免疫細胞が集まっており、のどの見張り番のような働きをしています。

名前の由来=「扁桃」という字は、「扁平なかたちの桃=アーモンド」に似ていることから来ています。
たしかに、口蓋扁桃もアーモンドくらいの大きさで、ちょっと似ていますね🌰
(c) 喉頭・気管・気管支
喉頭までは上気道の一部ですが、ここから先の気管・気管支は下気道にあたります。
肺へとつながる“空気の通り道”として、この3つはまとめて押さえておくと覚えやすいですよ。
■ 喉頭(こうとう)
- 咽頭の下にあり、声帯がある場所。
- 息を吐くときに声帯が振動して、声を出す働きをします。
■ 気管(きかん)
- 気管(きかん)
気管は、喉頭のすぐ下から始まり、肺に向かって空気を運ぶ“太くてまっすぐな管”です。
長さはおよそ10〜12cm、内径は約2cmほどで、大人の小指ほどの太さと言われます。
🛡️ 働き:
空気を気管支→肺胞まで確実に送り届けるルートとして重要。
内側は線毛(せんもう)と粘液をもつ粘膜で覆われていて、
ホコリ・細菌などをキャッチして外へ追い出す仕組みになっています(=線毛運動)。 - 約10~12cmの長さで、軟骨でできたリング構造が支えています。
■ 気管支(きかんし)
- 気管が左右に分かれて肺に入っていく枝分かれの道。
- さらに細かく枝分かれしながら肺胞(はいほう)につながる構造です。
📝 ポイント:
気管や気管支の内側も粘膜でおおわれており、異物や細菌の侵入を防ぐ機能が備わっています!
(d) 肺(はい)
呼吸器系のゴール地点で、ガス交換(酸素と二酸化炭素の交換)を行う臓器です。左右に1つずつありますが、右肺の方が少し大きいのが特徴です。
主な働き:
- 気管支が細かく枝分かれしていく先にある「肺胞」で、酸素を取り込み、二酸化炭素を排出する。
- 肺胞はぶどうの房のように小さな袋がたくさん集まった形で、表面積が非常に広いです(←ここもよく出ます)。
📝 ポイント:
このガス交換によって、全身の細胞に酸素が送られ、不要な二酸化炭素が回収されて外に出されます。
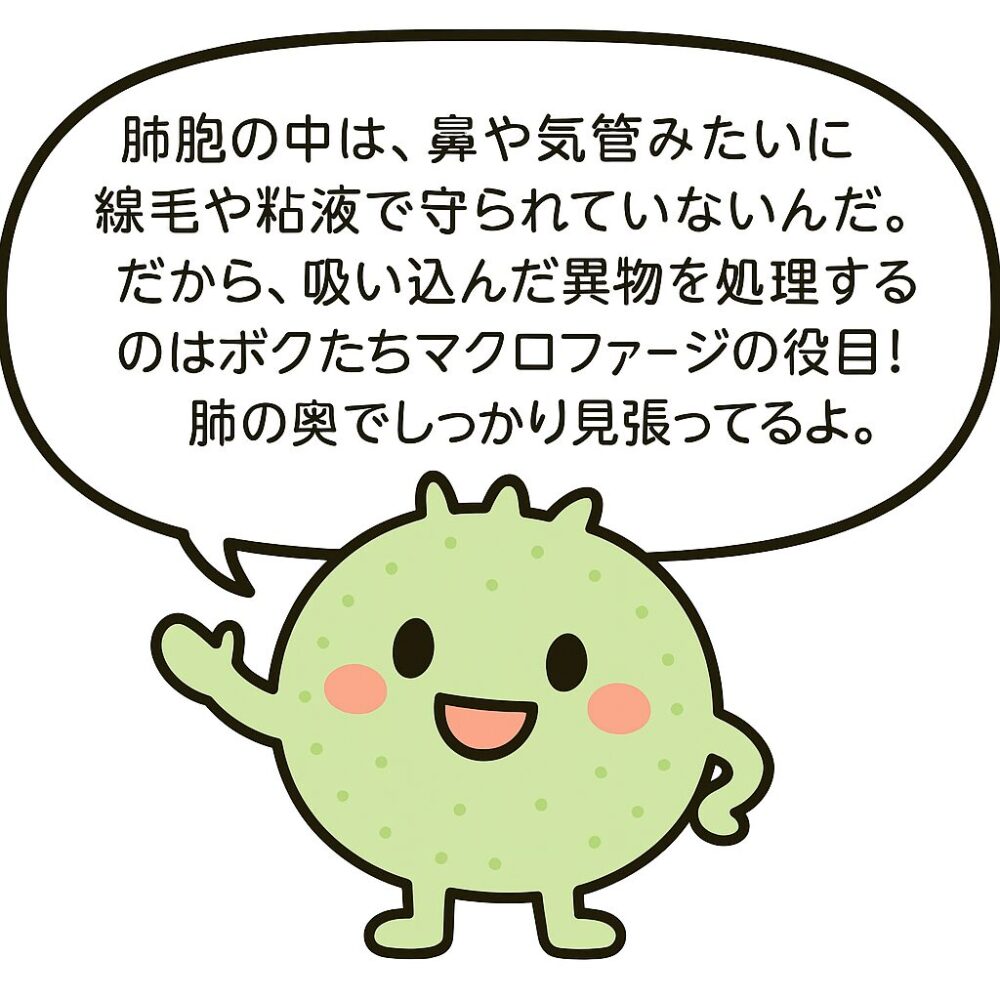
画像:ChatGPT
✏️まとめ:用語と役割を整理!
| 用語 | 部位 | 主な働き |
|---|---|---|
| 鼻腔 | 上気道 | 空気の加湿・加温・ろ過、リゾチームで防御 |
| 咽頭 | 上気道 | 空気と食べ物の通り道の分岐点 |
| 喉頭 | 上気道の終点 | 声帯があり発声、異物をブロック |
| 気管・気管支 | 下気道 | 肺への空気の通り道、粘膜による防御 |
| 肺・肺胞 | 下気道の終点 | 酸素と二酸化炭素のガス交換 |

呼吸器系は、空気を体に取り込み、不要になった二酸化炭素を体外に排出するという、まさに「いのちをつなぐ」大切な働きを担っています。
鼻や気管、肺の仕組みを通して、酸素がどのように体内をめぐるのかを学んでみると、日ごろ何気なくしている呼吸にも新たな気づきがあるかもしれません。
医薬品のはたらきについても、「気道を広げる」「咳をしずめる」「痰を出しやすくする」など、それぞれの薬がどこにどう作用しているのかをイメージすることで、覚えやすくなりますよ。
次回からは、いよいよ「循環器系」に入ります。
血液や心臓、血管といった“めぐり”の仕組みは、人体の理解を深めるうえでとても重要なテーマです。
覚える用語は少し増えますが、「流れをとらえること」が大きな助けになりますので、楽しく進めていきましょう!







【第9回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:腎臓)
【第10回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:副腎)
【第11回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その2:尿路)
