【第4回】第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
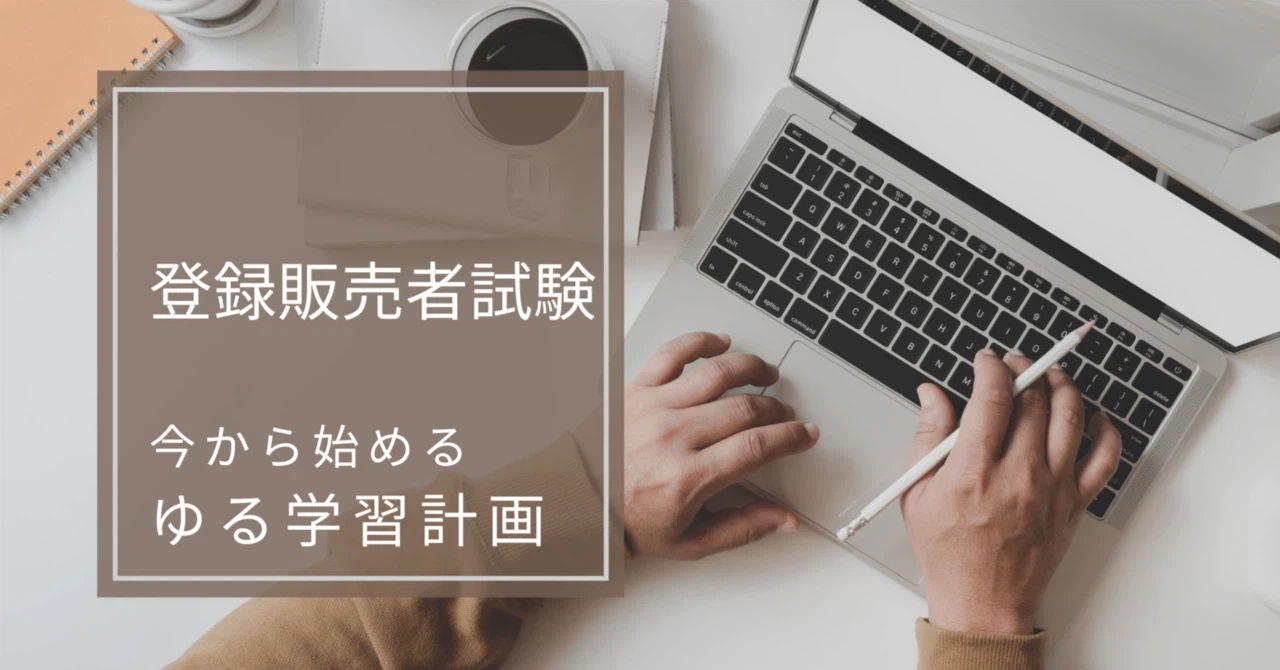
今から始める!登録販売者ゆる学習計画【第4回】第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識
こんにちは。いよいよ今回は「第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識」をざっくりチェックしていきます!
この章は、登録販売者として医薬品を販売するうえで基本となる「そもそも薬って何?」「副作用ってどう考えるの?」といった根っこの部分がまとまっています。
試験でもよく出る範囲なので、手引きの項目ごとに簡単に解説していきますね。
Ⅰ 医薬品概論
1)医薬品の本質
医薬品とは、疾病の治療・予防を目的としたものであり、効果の反面、副作用などのリスクも伴う特別なものです。
だからこそ、適正使用がとても重要になります。
また、医薬品は市販後にも、医学、薬学などの新たな知見、使用成績に基づき、その有効性、安全性等の確認が行われる仕組みになっています。リスク区分の見直しなどもあり、販売時の取り扱いが変更になることもあります。私の記憶に新しいことでは小児におけるコデイン類を含む医薬品の販売についての変更がありました。
これは、2019年より12歳未満の小児に対して禁忌となるという方針が、厚生労働省より通知されたことによるもので、当時、子供用の風邪薬や咳止めシロップにこのコデイン類が配合されたものは販売されていましたが、禁忌になったことで店頭から消えていきました。現在では、コデイン類の代わりに、脳の延髄にある咳中枢に作用して咳を抑える非麻薬性のデキストロメトルファンなどの成分が使われるようになっています。そう言えば、塩化リゾチームなどの成分も店頭から消えていった成分の一つです。

覚えられるかな?と不安になったあなた、ドラッグストアや薬局などに勤務していれば、会社からちゃんと情報が下りてくるので大丈夫。ただ、連絡に遅れがあったり、ばたばたした日常業務に追われて見落としてしまったり、パートタイムなどの短時間勤務や、急な休みが続いたりして伝え忘れがある可能性もあるかもしれないので、自分自身でもアンテナを立てて、受け身ではなく、進んで情報をキャッチする姿勢も大事です。
同僚がいる場合は、お互いに『あの変更、もう聞いた?』と普段から、お互いに情報を共有する関係を築いていれば、店舗のみんなで成長していけるはずです。
2)医薬品のリスク評価
医薬品は、「ベネフィット(効き目)」と「リスク(副作用など)」のバランスを見て判断されます。
このバランスを見極めるのが「リスク評価」であり、登録販売者もその視点を持つことが求められます。

身近な例でいうと、花粉症のお薬なんかがわかりやすいかもしれません。鼻水などの症状は止めたい。でも、第一世代の抗ヒスタミン薬では眠気や口の渇きといった副作用が出やすいのです。仕事や集中力が必要な時は副作用の出にくい第2世代の抗ヒスタミン薬のほうがいい場合もあります。お薬を飲む方の体質や状況によって、効き目や速効性を選ぶか、副作用の少ないものを選ぶか。お話を伺いながら、バランスを見てお薬のご提案をさせて頂きましょう。
3)健康食品
「薬じゃないけど体に良さそうなもの」が健康食品。
医薬品と違って、効果や安全性について国が評価しているわけではないため、「治る」といった表現は禁止されています。
薬との違いを知っておくことが大切です。
- 特定保健食品
- 栄養機能食品
- 機能性表示食品

この3つの違い、答えられますか?それらしい文章が並べられて、その正誤を問う問題も多いのでしっかり頭に入れておきましょう。店頭で商品のラベルを読んでみるのも印象に残りやすいですよ。
4)セルフメディケーション
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てする」という考え方。
医療機関を安易に利用せず、OTC医薬品(市販薬)を上手に活用することが求められています。
登録販売者は、その支援をする役割を担っています。
また、平成29年1月より、セルフメディケーションを推進するため、所得控除を受けられるセルフメディケーション税制が導入されています。
◆セルフメディケーション税制って?
かぜ薬や胃薬など、対象の市販薬(スイッチOTC医薬品)をたくさん買った人が、確定申告でお金が戻ってくる制度です。
年間1万2,000円以上の購入で使えるので、ふつうの医療費控除(10万円〜)より使いやすいのが特徴です。
ただし、対象になる薬のレシートをとっておくことや、健康診断を受けていることが条件です。
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか使えません。
✅ 医療費控除とのちがい(ポイント比較)
| 比較項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 病院・薬局の医療費全般 | スイッチOTC医薬品(対象品目) |
| 控除の適用条件 | 年間10万円超(or所得の5%超) | 年間1万2,000円超の購入が必要 |
| 他制度との併用 | セルフメディケーション税制とは併用不可 | 医療費控除とは併用不可 |
| 健康管理の実施要件 | 特にない | 健康診断・予防接種などの実施が必要 |

セルフメディケーション=「予防」や「自分で健康を守ること」
市販薬を上手に使って医療費の節約にもつながる制度です。
*詳しくは国税庁のHPや、勤務先のマニュアルなどをご確認くださいね。
Ⅱ 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因
1)副作用
副作用とは、「疾病の予防、診断、治療のた め、又は身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応」
これはどんな薬でも起こる可能性があり、使用者の体質や体調、併用薬によって違ってきます。

薬理作用、主作用、副作用、アレルギーという言葉について確認しておきましょう。特に副作用、アレルギーについてはお薬の販売時、お客様にしっかりと確認が必要です。お悩みの症状を聞いてみると、実はその原因が摂取されていた食品やお薬の副作用ではないかと考えられる事例もありました。年齢、アレルギーの有無、妊産婦でないか、基礎疾患の有無、現在すでに服用中のお薬との飲み合わせの可否なども重要な情報です。副作用を知っていると、必ずお尋ねする必要があることの理由もわかってきますので、しっかりと押さえておきましょう。
2)不適正な使用と副作用
用法・用量を守らなかったり、自己判断で飲み続けたりすると、副作用のリスクが大きくなります。
「正しく使うこと=副作用を減らすこと」だと覚えておきましょう。

一般用医薬品は、ドラッグストアなどで手軽に買える便利なお薬です。
でもその「手軽さ」が、かえって誤った使いや思い込みによるトラブルにつながることもあるんです。
たとえばこんなケース、思い当たりませんか?
薬を飲んでいるのに症状が良くならないのに、そのまま使い続けている
「とりあえず薬で何とかなる」と思って、生活習慣の見直しや病院の受診を後回しにしている
「たくさん飲めば早く効く」と考えて、決められた量以上に服用してしまう
子どもに大人用の薬を半分にして飲ませる、という自己判断
こういった使い方は、副作用のリスクを高めたり、病気を見逃したりする危険性があります。
しかも、医薬品によっては長く使い続けることで、肝臓や腎臓などの臓器を傷めることもあるんです。
たとえば、
便秘薬を毎日のように使う
頭痛薬や風邪薬を、習慣のように飲み続けてしまう
このような「長期連用」は、重い病気のサインを見逃すことにもなりかねません。
さらに、薬に頼るクセ(精神的な依存)がついてしまうと、気づかないうちに使う量が増えたり、お金の負担も大きくなってしまうことも…。
こうした事態を防ぐために大切なのが、
登録販売者など、販売に関わる専門家の正しい説明と、購入者の正しい理解です。
購入者の方には、「添付文書をしっかり読むこと」「決められた使い方を守ること」が求められますが、
その前提として、わかりやすく説明すること、相手の理解力に合わせて伝えることが、販売に関わる私たちの大切な役割なんですね。
3)他の医薬品や食品との相互作用、飲み合わせ
薬と薬、薬と食品が影響し合うことを「相互作用」といいます。
たとえば、グレープフルーツと一部の薬の飲み合わせは有名ですね。
4)小児、高齢者等への配慮
子どもや高齢者は、代謝や感受性が異なるため、副作用が出やすいことがあります。
年齢や体格を考慮して、安全な提案をする必要があります。
特に乳児の場合は時には一般用医薬品による対処は最小限にとどめ、医療機関の受診を優先することが大切です。
高齢者の方が医薬品を使うときに気をつけたいこと
高齢の方の中には、もともと持病をお持ちの方も少なくありません。
そのため、市販薬(一般用医薬品)を選ぶときにも、体に合わない成分が含まれていないかに注意することがとても大切です。
市販薬は手軽に買える分、気軽に使いがちですが、持病があると「かえって悪化させてしまう」「副作用を起こしやすくなる」といった心配もあります。
どんな成分があるのか、どんな影響があるのか、必ず確認しておいてくださいね。
✅ 妊婦さんや授乳中の方に市販薬を使うときは、とくに慎重に!
妊娠中や授乳中の方は、体調が変化しやすく、とてもデリケートな時期です。だからこそ、市販薬を使っていいのかどうかは、自己判断せずに専門家に相談することが大切です。
💡妊婦さんの場合
- 妊娠中は、ちょっとした体調変化でも不安になりやすく、市販薬に頼りたくなることもありますよね。
- でも実際は、薬の成分がどのくらい胎児に届くのかはまだよくわかっていないものも多く、妊婦さんが使った場合の安全性もはっきりしないことがほとんど。
- そのため、市販薬では「妊婦または妊娠していると思われる方は、医師または薬剤師に相談すること」と記載されているものが多くあります。
📝 個人的な意見としても、妊婦さんへの市販薬の販売は、基本的にはなるべく控えるべきだと考えています。
なぜなら、購入者の母体の健康状態を私たちが把握することはできないからです。思わぬ副作用やリスクを避けるためにも、まずは主治医に相談することが最優先だと思っています。
🔸市販薬の販売時には、「この薬を使っても大丈夫か?」よりも、「そもそも市販薬で対処していい状態か?」を一緒に考えることが大切です。
🔸そして、妊娠の有無は非常にプライベートな情報。質問する際には、まわりに人がいないタイミングや言い回しにも配慮しましょう。
👶 授乳中の方の場合
- 一部の薬は、母乳に成分が移行して、赤ちゃんに影響を及ぼすことがあります。
- 授乳中に避けたほうがよい薬や、服用中の授乳を避ける必要があるものもあります。
🔍 相談を受けたときには、薬が母乳にどれくらい移行するのか、赤ちゃんにどんな作用が出る可能性があるのかを、しっかり説明できるようにしておきましょう。
✅ まとめ:販売時の聞き取り+配慮がカギ!
- 「妊娠していますか?」「授乳中ですか?」といった質問は、周囲の状況に配慮しながら丁寧に。
- 添付文書の「相談すること」「使用上の注意」「してはいけないこと」をしっかり確認。
- 妊婦さん・授乳婦さんからの相談には、市販薬をすすめるよりも、まずは医師に相談するようお伝えするのが安心です。
正しく使うために、事前のチェックを
高齢の方が市販薬を使うときは、
✅ 持病と飲み合わせに問題がないか?
✅ 添付文書(説明書)の「してはいけないこと」「相談すること」にあてはまる症状はないか?
✅ 心配なときは医師や登録販売者に相談すること
これらを意識することで、医薬品をより安全に使うことができます。
とくに複数の持病がある場合は、ひとつの薬でも影響が重なりやすくなるので、自己判断で市販薬を選ばず、相談しながら選ぶことがとても大切です。
5)プラセボ効果(プラシーボ効果)
本物の薬じゃなくても、「効くかも」という気持ちだけで症状が軽くなることがあります。
これは「プラセボ効果」と呼ばれ、医療現場でも一定の影響が認められています。
6)医薬品の品質
医薬品は、製造・保管の管理が厳しく定められています。
品質のばらつきがあると、安全性にも影響が出るため、適切な管理が不可欠です。
Ⅲ 適切な医薬品選択と受診勧奨
1)一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲
登録販売者は、「この症状なら市販薬で対応できそうか?それとも病院に行くべきか?」を判断する役割があります。
市販薬で対応できる軽い症状の見極めがポイントです。

気を付けないといけないのが病院に行くのが嫌なお客様が、あえて情報を正しく伝えない場合です。「とにかく効くお薬を!」などとおっしゃられる場合は、他にお試しになっても効かなかった経験があるのかもしれません。どのような症状で、どんなものを試してみられたか、何にお困りなのかをお客様のお話だけでなく、こちらからも質問をして、原因と対処法を一緒に探っていきましょう。お薬は強ければ効くというものではなく、いかに症状にあったものを適切に服用していただけるかが大切です。私の経験では、目の前がチカチカするから目薬を、とのご相談で市販薬で何とか治そうとされるお客様を、重大な症状と判断して受診勧奨したことがあります。その後、眼科に行かれたお客様から、網膜剥離をしかけていた、受診を勧めてくれて本当にありがとうと、お礼の言葉を頂いたこともあります。
必要であれば、お薬の販売を見合わせて、受診を勧めることも大切な仕事の一つです。
2)販売時のコミュニケーション
相手の話をしっかり聞き取り、正しい情報提供とアドバイスができるかが大切。
対話を通して、安全に薬を選んでもらう支援をします。
Ⅳ 薬害の歴史
1)医薬品による副作用等に対する基本的考え方
薬害の歴史を踏まえて、「副作用から使用者を守るしくみが必要」という考え方が確立されました。
リスクに対して敏感であることが、今の医薬品制度を支えています。
2)医薬品による副作用等にかかる主な訴訟
例)サリドマイド訴訟、スモン訴訟など、重大な薬害事件を通じて、薬の安全性に対する取り組みが強化されてきました。
背景を知ることで、なぜ「慎重な販売」が求められるのかが見えてきます。

医薬品副作用救済制度の創設されたきっかけとなる二つの訴訟はしっかり覚えておきましょう。また、HIV,CJDなど、生物由来製品による感染症がきっかけで作られた感染等被害救済制度も合わせて覚えておきましょう。何が原因でどうしてしまったからそのような被害が生まれることになってしまったのか、流れを含めて覚えおくと、正誤問題で正しい答えを選べるでしょう。
まとめ|第1章は薬の“基礎のキソ”
この章では、薬の特性、副作用の考え方、使い方の注意点、過去の教訓まで、薬を安全に使うための「心構え」が詰まっています。しっかり覚えておきましょうね。
次回は「人体のしくみ(第2章)」をざっくりチェックしていきましょう!
✅ 次回予告
第5回|【第2章】人体の働きと医薬品|ざっくりわかる体のしくみ&出やすい範囲とは?
体のどんな部分に、どんな薬が効くのか?イメージしやすく解説していきます!







【第9回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:腎臓)
【第10回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:副腎)
【第11回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その2:尿路)

(アフィリエイト広告を利用しています)
